|


パリ郊外の加納家のエステートは本宅よりも更に広大なスケールを持つ。
起源は実に十六世紀にまで遡るシャトーだが四十年間に渡って放置されていたものを二十数年前、修三氏が買取り、五年の歳月と莫大な費用をかけて修復した。パリの市内からはかなり地方に入ることもあってもともと自然が豊かな場所だが、エデンとも言いたいような深い森を抱く庭園に囲まれて、至る所にゆったりと水路が流れている。
数百年の齢を経た巨木が小道の両側におびただしく並んで夏の陽光を遮りながら煌き、森に点在する古い彫刻もまた、長い間そこに据えられて風雨にさらされて来たものだ。本邸にあたる城の建物や内装もすばらしいが、何よりもこの神秘的な庭園の佇まいによってフランス中でも特筆される存在となっていた。
ウォルターたちはパリでのスタジオ録音を済ませると、ここに機材を運びこんでしばらく仕事をすることにしていたが、スタッフと一緒に車四台で乗りつけてはみたものの、そのエントランス・ファサードの荘厳な光景にウォルターばかりかダンもドリーも圧倒されてしまい、しばらく口もきけなかったほどだった。
これは自動車のような不粋な乗りもので乗りつけていいような場所ではない。
それこそ四頭立ての見事な馬車で、土埃りを蹴立てて通らせて頂かなくてはもったいないほどの門柱は両側に巨大な彫刻を戴き、英国式の迷路のような庭園を配してその向こうにアイボリーを基調とした優美な城が横たわっている。一行を丁重に迎えてくれたのはこの屋敷の管理を任されている執事のフランソワ・アルトワで、何人ものメイドがそれに連なっていた。
柱廊式の玄関から中に入ると、弧を描いたホールはイタリアのカララから運ばれたと伝えられる大理石でモザイクを施した床と、均等に配置された彫像でバランス良く飾られ、幅の広いステアケースが二階に向けて伸びているのが見える。そこからはもう空気の香りと流れでさえ全く別の空間だった。
聞いてみるとこの敷地の中には他に三つの小さな小邸宅があり、そのひとつに付随する厩舎には数頭のサラブレッドまでいるのだという。フランソワは人好きのする笑顔を浮かべて、宜しければいつでもお乗り頂けます、と言っていた。達者な英語で他に五か国語くらいは軽いらしい。いろいろな国から招かれるゲストをおもてなしすることもあるのだから、そのくらいでないと務まらないのだろう。
*****
次の日、音響効果が最も得られそうなホールにセッティングが完了してすぐに録音を開始したが、思ってもみなかった環境に囲まれてウォルターには新しいメロディ・ラインが次々と浮かんで来てしまい、予定していなかった楽器なども使いたくなって、ここでの仕事は相当長引きそうだった。なんだかディスク2、3枚分の曲ができちゃうかも、とウォルターは冗談を言っていたくらいだ。
彼は早朝から森を散策するのが楽しいようで、まるでお伽話の世界に魅せられてしまったように、ひまを見つけると飽きもしないで歩き回っていた。
どこに続いているんだろう、と延々と曲がりくねった小道を歩いて行くと、突然、中世風の石造りの小邸宅が現れたり、今にも生き返って動き出しそうな半獣神や女神の彫像が視界に飛びこんで来たりするのだから無理もない。その中には湖のほとりに造られたどこか日本の香りのするアングロ・ジャパニーズ・スタイルの庭園や、花々に彩られた、その周辺自体がひとつの公園とも思えるスケールの大きなファウンテンもあった。行けども行けども際限のない驚きが一歩先には待っていて、時には木陰でひと休みしているうちに涼やかな風と鳥の囀りが心地よくて眠りこんだりしてしまうほど、平穏に満ちた楽園とも呼びたいような庭なのである。
録音も順調だし、季節も緑豊かな初夏だし、と、その日もウォルターが幸せな気分で歩いていると、ふいに遠くから馬の蹄の音が近づいて来た。あれ、と思って振り返った彼の視界には、漆黒に輝くみごとなサラブレッドがこちらに向かって駆けて来るのが見える。ウォルターがそのあまりの背景との調和に、まるで絵でも見ているような錯覚に囚われて立ち尽くしていると、その姿はみるみるはっきりとして来て、彼の近くまで来ると騎手は鮮やかに手綱を引いて馬を止めた。
「やっと見つけた!毎日ふらふら散歩に出かけちゃ迷子になって喜んでるってダンが言ってたけど・・・」
馬から滑り降りた相手が言うのを聞いて現実に戻り、ウォルターは驚いている。
「こんちわ、がんばってるそうじゃない」
綾は笑って彼を見た。
「やあ・・・」
「どうしたの」
幽霊でも見たみたいなウォルターの表情に、綾は不思議そうに尋ねた。
「・・・どうって。こんにちは。・・・へえ、本当に来てくれるなんて驚いたな」
「パリまで用事があったからね。丁度仕事が一段落ついたとこだったから、ついでに二、三日のんびりしようかな、と思って」
「そうなの」
二人はなんとなく並んで歩き出した。馬は綾が手綱を曳いて促すのへ、おとなしい性質なのか素直について来る。
「あんまり綺麗なんで夢でも見てるのかと思ったよ」
ウォルターが言うのへ綾は何が、と問い返した。
「馬と・・・、それからきみ。こんな中世のお城でさ、庭と言うにはここ殆どセントラル・パークみたいに広いし、そこへ馬なんて。映画みたいなんだもの」
綾は笑っている。
「なんだかなー。ほんとにこんな世界があるなんて。信じられないくらいだよ」
「楽しんで頂いてるみたいで嬉しいけどね、仕事の方はどうなってるの」
「そりゃあもう最高です。毎日殆どリテイクなしで決まっちゃうしさ。何もかもきみのおかげだよ。感謝してます」
「そんなのしなくっていいさ。あんた才能あるもん。ま、実業家としちゃ、いい投資ってとこかな。気にしないで」
「ね、ダンが言ってたけど、きみって本当にお父さんの仕事手伝ってるの」
「まあね」
「信じられないな」
「どうして」
「だって、・・・まだ十七才なんだろ」
「そうだよ」
「女の子だし」
「そんなの関係ないじゃない」
「すごく有能なんだって?」
「それはご想像におまかせします」
綾はにっこりしてウォルターを見た。その無邪気な笑顔に当惑しながらウォルターは言った。
「十七才の女の子、なのにね、全く見た目は」
「・・・・・」
他の誰かが ― 例えばスティーヴでも ― 言ったんだったら、まずただですむセリフではない。"十七才の女の子"、そう見られることが綾は何よりもキライだ。
それは彼女個人の本質とあまりにもかけ離れていて自分を見誤られているという不当な感じがするし、その明らかな誤解をどこかで裏切らなければならなくなる、うしろめたい気持ちがそうさせるらしい。けれどもウォルターの言うのは無邪気なせいもあるのか、怒る気にはなれなかった。
「普通ならハイスクールじゃない。ぼくの知ってるそのくらいの女の子と較べても・・・」
言ってふいにウォルターは黙り、しばらくして納得したように頷きながら続けた。
「なるほど。やっぱりきみってずいぶん違うんだ」
「・・・違うって?へえ、どう違って見えるの」
綾はふいに好奇心にかられて尋ねていた。めったにそんな風に言う人がいないからだ。
綾の外見にだまされて、たいてい初対面やそれに近い人たちは彼女をお嬢さま扱いする。まあ、綾がネコをかぶりっぱなしにしている場合もよくあるのだが。
「どう、って言われても。むずかしいね、説明するのは。なんかね、空気が違うっていうのかな。やっぱりいろいろ・・・、普通の女の子と違うことやってるからなんだろうけど。仕事とかも。・・・ああ、そうか、それにきみってお姫さまなんだ」
「なんだよ、それー」
綾はしかめっつらをした。
「ダンが言ってた。すっごいお金持ちのお嬢さまなんだぞって」
「ダンのやつ。はた迷惑なやつだな、もお。どうせろくなこと言われてない気がするぞ」
ウォルターはくすくす笑って続けた。
「きみってでも、ものの言い方とかさ、全然そんな感じしないから。・・・面白いだろって言ってたな、彼」
「面白くて悪かったね」
「おてんばなお姫さまで生意気な上わがままで」
「そらみろ、やっぱりそういう落ちだろ、あのやろー」
「でもダンってきみのことすごく好きみたいだ」
「・・・・・」
「嬉しそう、というかさ、そう言ってる顔が。・・・ぼくもなんかわかる気がする。うん、そうだ。一言で言えば曲になる感じだ」
「曲?」
「そう」
「どんな」
「口じゃ言えないよ。・・・きっとそのうち出来るから、そうしたら聞かせてあげるね」
いたずらそうに彼はにっこりした。どうもこの素直な笑顔にかかると綾はものが言えなくなる。どういう奴なんだろう、と彼女は改めて興味を引かれていた。
「ね、それより食事がすんだら一曲聞かせてくれない?楽しみにしてたんだ」
「もちろん。一曲と言わず何曲でも。リクエストがあればカヴァーもやっちゃうよ」
ウォルターは嬉しそうに答えている。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.8.11.
revise : 2010.11.28.
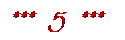

|
![]()