|

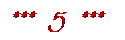
それからしばらくウォルター達はレコーディングの準備に追われていたらしいが、春から夏を迎える頃になってダンから綾の東京のオフィスへ電話が入った。RMCと組んでウォルターのことは全面的に彼とドリーが面倒を見ることになったと張り切っている。彼にしてみると長いことやりたかった仕事でもあるらしい。
「で、さ、この際スタジオなんかもいくつか使って録りたいと思ってるんだ。あいつもいろんなとこでアルバム作るのには参加してるからね、いろいろと希望もあって。ただスポンサーの意向も聞いといた方がいいかな、と」
綾は彼が自分のことのように舞い上がっているのがおかしくて仕方なかった。
「はいはい。好きなようにやっていいよ、言ったでしょ」
「パリとね」
「うん」
「バハマにも行きたいなーって言ってるんだ。わがままかなっ」
「どうぞ行ってらして下さい」
「ほんと」
「ほんと。・・・え、と、パリとバハマって言ったの」
「そう。で、仕上げはニューヨーク帰ってね」
「それだとどっちにもうちの家があるから、スタジオから遠くなきゃ使うといいよ」
「えー」
「いつ誰が行ってもいいように人揃えてるから。普通のホテルなんかよかずっと落ち着くと思うよ」
「おたくの別邸だろ」
「うん、そう」
「いいのかなあ、ほんと。話に聞くところによると、殆どお城って言うじゃない」
「城があるのはドイツとフランスのいなか」
綾の答えに、ダンは絶句している。
「どうせこれから暑くなるし、ベンとドリーも連れてけばいいのに」
「えー、でもそこまでは。・・・ドリーも仕事あるしな」
「向こうでプロモーション用の写真撮りとかもすれば?なんてったってRMC期待の新人、なんだからさ」
「いいね、それ」
「ご家族揃ってご招待するよ」
言われて一瞬、何と返していいのか分からなかったらしく、ダンは再び言葉を失ったようだ。
「どうかしたの?」
「いいやつだなあ、姫って」
「ほんと調子いいんだから。で、あと何かあるの」
「使うミュージシャンなんか知りたくない?」
「教えて」
綾にも興味は充分にあった。あのテープで聞いた曲がどんなレコードに仕上がるのかちょっと見当がつかない。
「いちおうね、あいつの友達でスケジュールが合ったの一人でさ。あとの二人は売れっ子のスタジオ・ミュージシャンだから手があかなくて。でも・・・」
と、彼が列挙していった名前はけっこう綾にも馴染みがあったし納得できた。
「日本人もね、いるんだ。知ってる?立原 淳和(じゅんな)っていう・・・」
「そいつってロンドンに住んでるだろ」
「そう」
「ルイス・キャロルの佐竹 満の従兄だよ」
「よく知ってるな」
「キャロルは好きだしね。あいつの親父の会社がうちの系列だし」
「なるほど」
「日本でロックバンドなんて言えるようなしろもの、キャロルくらいしかないだろ」
「・・・自国の恥をよく知ってるみたいだな」
「悪かったな。どこへ行っても外国行くとそれで苛められるんだから。音楽どころか果ては文壇と呼べるようなものがあるのか、と、マジで聞かれたりするんだぞ。才能のある人はみんな海外へ出ちゃうじゃないかって。こっちだって悲しい思いは毎日してるよ」
ダンは電話の向こうで笑っていた。
「アレックなんて一番てごわいんだから」
「ニコルソン卿かい?」
「そう。こないだなんか自分でものの価値もつけられない分際で逆輸入だけは一人前だな、とののしられた。ぼくがやってんじゃないのにぃー」
「はいはい」
「苦労してるんだ」
「わかるよ」
同情した声で、けれどもくすくす笑いながらダンは言っていた。
「で、まあ、そんなとこだな」
「始めはパリなの」
「そう」
「行こーかな。おじゃま?」
「そりゃかまわないけど」
「面白そうだし、時間があったら寄るかもしんない」
「待ってるよ」
「何かあったらここに連絡しておいて」
「そうする」
「じゃあね」
そんなわけでウォルターのレコーディングは始まることになった。
これからしばらくするとニューヨークは熱暑への一途をたどる。パリから彼らがカリブ海に移る頃には地獄みたいになっているだろう。秋になる頃にどんなディスクが仕上がっているか、綾には久しぶりに楽しみなことが出来た。けれども秋になる頃に自分がどんな目にあっているか、まだ彼女には知る術もなかった。
一方、ロックウェル家では、ニューヨークからパリへの出発準備に文字通りの大騒ぎが巻き起こっていた。話したとたんドリーもベンも大歓声を上げ、スーツケース五個が三日も置かずにいっぱいになったのである。ウォルターとニューヨークから一緒に行くことになっているスタッフを伴って、お姫さま差し回しの自家用機で彼らがケネディ空港をあとにしたのは、それから三週間ばかり後のことだった。
結局バハマでは予定通りスタジオを使い、パリでは市内でレコーディングしたあと、綾の言っていた郊外の城でもいくらか録ってみておこう、ということに落ち着いている。
「ぜーたくっ!」
ウォルターは機体が水平飛行に移ってからダンに言っていた。
機内のサロンは全体に落ち着いたブルーとオークの木目調で仕上げられ、弧を描いて配置された柔らかなソファと床の絨毯も同系の色でまとめられて目に優しい。壁には深みのある色あいの木のユニットが嵌めこまれ、同素材のオークを使った半円のテーブルには、ついさっきパーサーが並べてくれた小菓子と銀細工のティ・セットが乗せられている。セイレーン同様、ボーイング747の機体を改造したプライヴェート・ジェットだから、飛んでいるとは信じられないようなこの空間は、全く贅沢な応接室さながらのできばえだった。
「すごいだろ」
「うん」
「パリの別邸ってば年代ものの屋敷でさ、庭園なんかもお伽話に出てくるみたいだって言うぜ。その手の雑誌なんかでも何回も取り上げられてるからな」
「へえー」
「楽しみなのはバハマのヴィラの方よおっ、もおすっごくステキなのっ。プールなんか二つもあって、景色だってパラダイスよ。最っ高」
「よく知ってるんだね、ドリー」
「あたりまえじゃない。ヴォーグやハウスビューティフルでも特集したくらいなんだから、知らない方がおかしいってくらいのもんだわ」
すっかりはしゃいで彼女はテーブルの上の、ストロベリーにミモザをあしらったプティ・フールをつまむと口に放りこんだ。
「仕事・・・、だよね。ぼく、そう思って・・・」
「あら」
ドリーは思わず口を押さえた。
「いーんじゃないの、めったにあることじゃなし。おまえもさ、そう硬くならずに軽い気持ちで行きゃあいいんだよ、軽く」
大丈夫なんだろうか、とウォルターは二人を見較べた。しかし冗談ばかりでひょうきんなダンも、仕事となると人が変わることはよく知っている。ま、いいか、と思いながら、それとは別にウォルターにも楽しみなことがひとつある。
――― もしかしたらもう一回くらい会えるかな。ダンも言ってたし。なんたってぼくのスポンサーなんだから。会えるといいなあ。きれいな女の子だったな。人形みたいでかわいくって。
綾の外見と内面がまるっきり正反対なのをウォルターはまだ知らない。ともあれこの頃はまだその程度を楽しみに思っているだけで、これから創るディスクの方が何倍も彼には大切だったのである。
Book1 original text
: 1996.10.15~1997.1.15.
revise : 2008.8.11.
revise : 2010.11.28.


|
![]()