|


結局二週間後、綾はやっとの休暇を返上してロンドンからニューヨークへ飛んで来ていた。本当なら東京に帰って一日中ベッドにもぐりこんでいるところだ。ダンに言った通り、ろくに眠ってもいなかった。
「ふあーあい」
「イヤミなやつだな、まっぴるまにあくびなんかして」
「あれっ、嫌味ってわかるの、意外だなーっ」
綾はダンのオープントップのシヴォレーの助手席で眠そうにシートに沈みこんでいた。
「悪いと思うから迎えにまで来てるんじゃないか、おれだって」
「どーも」
彼女は語尾を上げて皮肉たっぷりに言った。
黒い革のパンツにブルーのシャツ、同じ柔らかい革で作ったジャケットを綾は着ている。サングラスをかけて、フラットキャップを目深にかぶっていた。
「ウォルター、折れないの」
「折れなかった」
「どういう奴なんだ、それって。ぼくにわがまま通した奴なんて初めてだ」
「そういう奴でね」
「あのみばからは想像もつかない」
「音楽ばかで世事にうとくて間がぬけてるくせに、一旦言い出すとてこでも動かない時がある」
「信じらんない」
「なあ、姫」
「なに」
「あいつは確信が欲しいんだと思う」
「なに、それ」
「自分の歌を気に入ってくれた誰かが本当にいるんだ、という確信」
「そんなものあんたやドリーでたくさんじゃないか、なんでぼくまで」
「それはあいつに聞いてくれ」
言いながら彼は車をゆるやかなカーヴにそって右折させて行った。
加納綾は大財閥のご令嬢、のみならず超多忙な実業家でさえある。ダン・ロックウェルは有名なプロデューサー、ミュージシャン志望の若い連中なら誰だって頭を下げても相手にしてもらいたい。アドリア・レヴァインは大手レコード会社の企画部長、実績あるキャリア・ウーマンで仕事がからむと決して私情は入らない。
ところがこの三人が全く無名の何の変哲もない ― はずの ― たかだか歌手の坊やのわがままに右往左往しているのである。本人はまるっきり意識もしていないのに決まっているが、ウォルターにはそんな起こりえないことを引き起こしてしまう何かがあるようだった。
*****
RMCレコードがマンハッタンにかまえる本社ビルは地上七十階を有し、淡いグレーに仕上げられた建物は数多い摩天楼の中でもひときわ美しい。エントランス部分には緑が数多く植えられて光彩を反射している。ダンのシヴォレーが、その大理石のエントランスに滑り込んで来ると、待ち構えていたサイモン・クライン以下、錚々たる重役連が丁重に出迎え、車を降りた二人は彼らに取り囲まれるようにして建物の中へ入って行く格好になった。
「うっとーしーからサイモンだけにしてくれっ、それともここはそんなにヒマなのかっ」
綾は寝不足でとことん機嫌が悪い。
あわてて散ってゆくおえらがたを見送りながら、ダンはこりゃーウォルターのやつ、ただですまねーな、と面白がっていた。綾だって、ただすますつもりは毛頭なかった。
休暇と言ったってたったの二日しかないのだ。あさっての午後には東京で重役会である。それをニューヨークくんだりまで遠回りさせられたんだから冗談ごとではない。
この頃の綾は加納家の後継者として非公式とはいえ既に認められていたから、修三さんの意向もあってフィールドワーク専門に回されていた。つまり最も忙しい時期だったのである。快適な自家用機と言ったって空を飛ぶ限り限界というものがあるのだ。どんなにクッションが悪くたって地上のベッドの方がずっといい。絶対怒鳴りつけてやる。綾は固く心に決めていた。
ところが応接室の扉を開いてさて、と一呼吸置いた時、ウォルターに先手を取られてしまったのだ。彼は綾が入って来るのを見たとたん、やった、大当たり、うそみたい、と大声で叫んだ。それで綾は、そしてダンも、わけがわからず答えようがないまま立ちつくしてしまった。
「やっぱり貴女だったんだ」
「ウォルター」
ダンがさすがに綾に気を使って、叱りつけるように言った。
「悪気はないとは分かってるが、いくらなんでもちょっと失礼だぞ、そういう態度。彼女には今度のことではものすごくお世話になったうえに今日は・・・」
ダンの言うのなどウォルターの耳には入っていない。彼はつかつかと綾に歩み寄ると、その手を取って素直にごめんなさい、と言った。
「忙しいひとだってドリーも言ったのに・・・。どうしても会いたくて」
「え・・・」
「貴女、半月ほど前ヴィレッジのライヴハウスに来てくれてたでしょう」
「・・・うん」
「やっぱりだ」
「どうしてそんなこと知ってるんだ?」
「まさかとも思ったんだけど東洋人の女の子だったし、RMCの会長って日本人だって聞いたことがあったから、もしかしたらと思って」
「ああ...」
「知らない人が本当に聴いてくれてるなって。ああいう気分で歌ったのも初めてで、・・・すごく幸せだったから」
「・・・・・」
「どうしても会ってお礼が言いたかったんだ」
ウォルターはどうもありがとう、と言って、日本式のつもりか丁寧に頭を下げた。それで綾は何も言えなくなってしまった。この手の素直さにはどこか勝てないものがある。彼女よりも背はずいぶん高いし、年だってダンの言うところでは七つも上のはずだ。、というのに、である。ダンが執心するのもわかるような気がした。
すっかり怒る気が失せた綾は、ついさっきまでの自分の余裕のなさに笑い出したくなって来た。彼女はしばらく黙っていたが、やがて言った。
「おまえ、さ」
「え・・・」
「恵まれない環境で歌って来たんだなあ、長いこと」
「・・・・・」
「全面的にバックアップしてやるから、やりたい放題好きなもん作れよ。金の心配しなくっていいから」
*****
「姫、待てよ、おいってば」
「なに」
廊下を先に歩いて行く綾をダンが追いかけている。
「おっどろいた」
「なにが」
「おれは開口一番あんたが怒鳴ると思ってた」
「ああ、そのつもりだった」
「それがなんでまた」
「その気が失せたの」
「のみならず金の心配はしなくていい、と来た。忙しすぎて気でも狂ったんじゃないの」
「知るもんか。気がついたら言ってたんだよっ」
「信じられない」
「自分でも信じられないけどね・・・」
言うと突然立ち止まり、彼女は振り返ってダンを見た。意味のありそうな微笑を浮かべている。
「でもさ、ダン」
「なに」
「たまには人間(おさるさん)に"歌"ってものを聞かせてやるのもいいんじゃないの」
彼はおっと、と思ったが、綾が本気らしいのへ滅多にしないプロデューサーの顔で答えた。まるっきりデッサンが狂っていない顔である。
「そりゃ、まあ・・・」
「プロデュースしてやってくれよな」
言うと綾はさっさと歩き出した。
「そんなものこっちからお願いするよ」
彼はまた綾を追いかけながら言っている。
「やあっぱりさ、おれの姫は最高だよ、ほんと」
「調子いいぞ」
「本気で言ってるんだってば。送るよ、ロングアイランドだろ」
「そんなとこまで行く余力が残ってるもんか。プラザでいい。あそこのスイート、借りっ放してるのがあるんだ」
一方、ウォルターはドリーの見守っている側でゆっくりと、けれどもしっかりと、契約書にサインしていた。
その晩アッパーイーストのロックウェル家で、彼を囲んで最高級のシャンパンを開ける音が響いたことは言うまでもない。ドリーのお手製のローストビーフにベンとウォルターは大歓声を上げている。丁度その頃、綾はキングサイズのダブルベッドにもちろん一人で沈みこんで、ひたすら眠りこけていた。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.7.29.
revise : 2010.11.28.

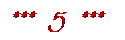
|
![]()